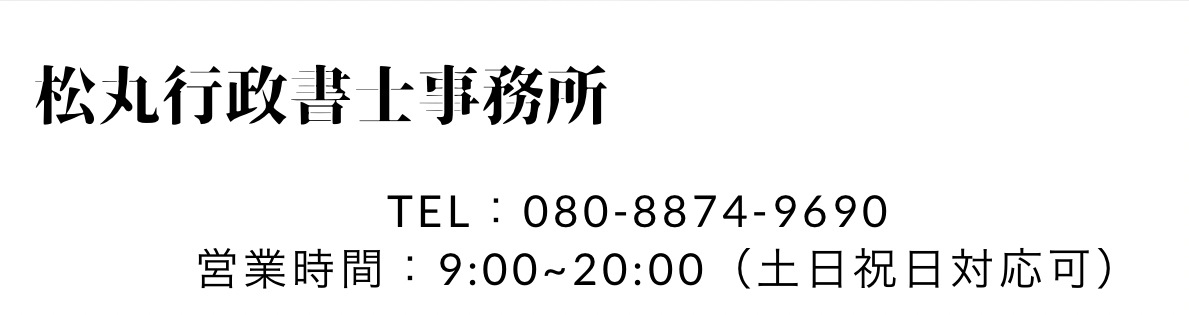技能実習生の在留資格変更申請ができなかった場合の監理組合の責任【国家資格者が解説】
在留資格の更新・変更申請は、基本的に本人が申請することが原則になっております。もっとも、技能実習生は、日本語能力が乏しいことから、これが難しいため、監理組合など取次申請することが認められています(※)。
しかし、在留資格の変更申請ができず、在留期間を超過したり、または、変更・更新が不許可になった場合、監理組合はどのような責任を負うことになるのでしょうか。
今回は、技能実習生の在留資格変更申請ができなかった場合の監理組合などの責任を、判例(令和5年9月28日大阪地裁)に基づき解説します。
※なお、監理組合等が入管に提出するための雇用契約書・申請書類等を作成している事案が見られますが、このような行為は、たとえ、作成行為自体が無償でも、管理費用などを受領している以上、行政書士法違反になります。罰金や懲役が課される行為になります。こちらを参考にしてください。

事案解説
このケースは、技能実習生である原告が、会社(=実習実施者)との間で雇用契約を締結し、建設業務に従事していたところ、会社が申請した技能実習計画について、在留期間中に外国人技能実習機構による認定が受けられず又は適切な説明を受けられなかったことによって在留期間更新許可申請をすることができず、雇用契約を契約期間の中途で解除したことにより、収入を失ったなどとして、 会社と監理団体に対して、不法行為による遅延損害金の支払を求めた事案である。
※監理団体とは、技能実習における支援機関みたいなもので、会社と技能実習生をサポートする機関になります。
責任の範囲
まず、「技能実習制度運用要領」で、技能実習計画の認定申請は、 実習開始予定日の6か月前から可能であり、原則として3か月前までに行う必要があるとされている。(本件では、満了日の2か月前に申請をしていた)
また、会社は実習実施者として、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について、責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努めなければならないとの一般的義務 を負っている。技能実習生が「技能実習」の在留資格を取得して本邦において適法に活動することは、技能実習の適正な実施の前提となる事項であり、技能実習を行わせる環境の基本的な構成要素ということ ができる。 このような本件雇用契約の目的及び内容並びに技能実習制度の仕組みに照らせば、被告会社は、原告に対し、原告が技能実習1号による在留期間満了までに技能実習2号への在留資格の変更ができるよう、技能実習1号による在留期間満了までに技能実習計画を作成して機構による 認定を受けるべき義務を負っていたというべきである。
さらに、在留資格変更申請を行うのは原告であるとしても(入管法上、在留申請は本人申請が原則である)、会社(監理団体を含む)は、技能実習生に対生、日本に在留しながら技能実習2号の在留資格変更手続を行うために取り得る手段の有無を調査して、これを技能実習生に対して説明すべき義務を負っていたと認めるのが相当である。(本判例時点では、在留期間満了日までに実習計画認定が下りない場合、短期滞在への変更を認めていたので、このような案内をすべき責任があるとされる。なお、現在は、一定の要件を満たすことで特定活動(就労可能)に変更できるため、このような案内を行うべきである。)
そして、被告会社は、労働基準監督署から是正勧告を受け、技能実習計画の認定を受けることができなかったのであれば、原告に対し、速やかに別の実習先にて技能実習を継続する希望があるかを確認し、その希望があれば、別の実習先にて技能実習を継続できるように連絡調整等の必要な措置を講ずべき法的義務があった。
まとめと結論
本判例とまとめると、
- 技能実習法の趣旨や目的に照らし、会社は、技能実習計画の認定を在留資格変更・期間更新までに行う必要があること。
- 会社と監理団体は、計画認定ができない場合に取りうる手段を技能実習生に説明する義務がある
- 認定計画を受けることができないのが予測されるのであれば、転籍の意思を確認し、転籍手続きを行う責任がある
上記にような責任が、監理団体や会社にあると言えます。
なお、本判例の結論としては、在留期間満了日から転籍先への就労開始日前日までの賃金相当額及び在留期間満了日から短期滞在の資格取得までの精神的苦痛による損害賠償請求を認めています。会社や監理団体の責任は、一般的な就労ビザと比べ、重たいと言えるでしょう。