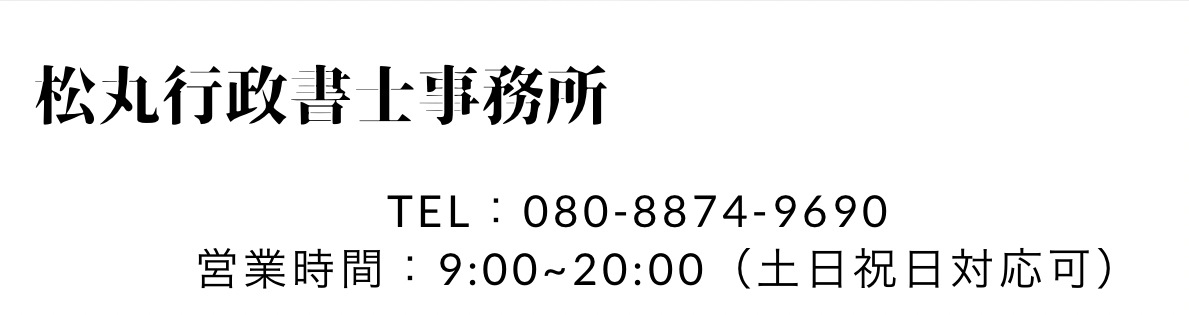旧民法の時に死亡した者の相続分と相続人は?【国家資格者が解説】
相続が発生した場合、外国籍でもない限り、民法の規定が適用されるので、ネットの情報と法律を確認すれば、相続人の特定と相続持分の把握は難しくはありません。
しかし、旧民法の場合、話が変わってきます。相続人が異なったり、相続持分は変わっていたり、一筋縄ではいきません。
今回は、旧民法における相続人の特定と法定相続分を簡単に解説させていただきます。

旧民法の適用時期
相続に関する民法の改正は下記のように分けられます。
- 旧民法:(明治31年7月16日~昭和22年5月2日) ※条文はこちらから
- 応急措置法の相続(昭和22年5月3日~昭和22年12月31日)
- 新民法の相続(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)
- 昭和55年改正(昭和56年1月1日~現在)
死亡した時期により相続人と相続持分は変わってきます。ただ、相続人は基本的には、変わっておらず、昭和22年以降に死亡した場合、その相続人は、配偶者と①子ども、②親、③兄弟姉妹の順番となります。代襲相続の回数とかの変更もありますが、そのようなケースの場合は、専門家に最初から相談したほうがいいと思います。
もっとも、相続持分は昭和22年5月3日~昭和56年1月1日と現在で変更がされていますので注意が必要です。相続持分の特定はややこしいので、ここでは割愛します。
旧民法時の相続人の特定と相続持分
旧民法(昭和22年5月1日まで)の場合、相続人も相続持分も現在と異なります。
まず、この時代の相続は、①家督相続と②遺産相続に分けられます。
家督相続は、戸主(戸籍を見ればわかります)の死亡や隠居(※)により、一人の家督相続人がすべてを引き継ぐことをいいます。つまり、戸主の地位とそれに附属する権利義務(家産)を、単独で承継するの制度です。
家督相続人は、原則、嫡出男子(長男→次男)のみです。もっとも、嫡出男子が死亡や国籍喪失していて、存在しないときは、認知された男子(庶生男子)、嫡出女子、認知された女子、非嫡出男子、非嫡出女子と続いていきます。私は、嫡出男子の相続したみたことないですね。
※隠居とは、戸主が60歳以上で、行為能力のある家督相続人が相続の単独承認を認めた場合に発生するものです(贈与みたいですね)。また、特別隠居という特別の事情を考慮し、裁判所の許可を得て行う隠居もあります。隠居後に取得した財産は、相続発生時に遺産相続として処理されます。
遺産相続とは、戸主以外が亡くなった際に適用するものです。こちらは現在の民法と近い制度になっており、①子ども(直系卑属)、②配偶者、③親(直系尊属)、④戸主と順番に相続人がなっていきます。相続持分については、同順位間で均等に分配されます。
なお、家督相続や遺産相続が生じていても、法定相続情報作成は可能です。詳細はこちらから。
旧民法以前に死亡していたら
私も一度しか見たことがないですが、旧民法以前に死亡した場合、明治31年7月16日以前に死亡していた場合どうなるのでしょうか。これ以前は、法律が明文されていないため、判断に迷うことがありますが、基本的には、慣習法などに基づき、家督相続の制度を用いることになります。