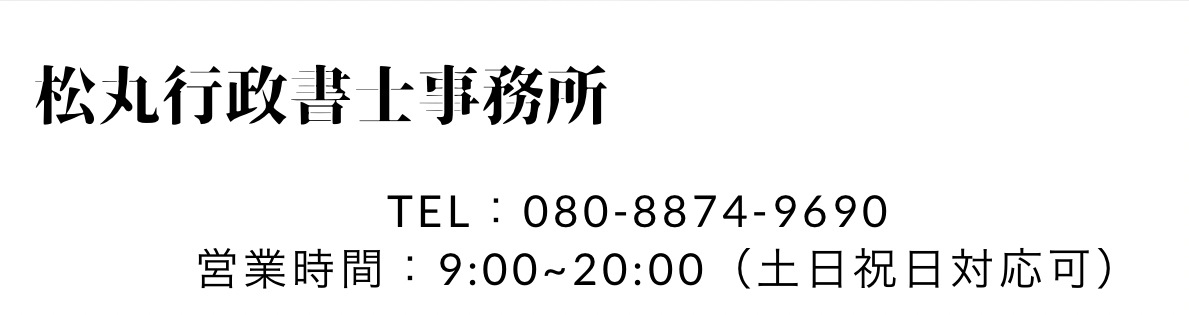生活保護受給者が相続人になった場合どうなる?【相続放棄するべきか】
生活保護を受給している人が、相続人になった場合、生活保護の打ち切りが生じるのではないかと不安になる方が多いかと思います。
生活保護の受給ができなくなるぐらいなら相続放棄してしまおうと判断される方もいますが、相続放棄をしてしまうと、ケースによりますが、相続手続が煩雑化し、他の相続人や親族に迷惑をかける可能性もあります。
今回は、生活保護受給者が相続を受けた場合の対応法を解説いたします。なお、ケースにより異なることが多々ありますので、詳細については、お近くの専門家(弁護士、司法書士、行政書士)にお尋ねください。当社のお問い合わせはこちら!

生活保護の受給ができなくなるケース
ここについては行政によりますが、通達によると、6か月を超えて保護を要しない状態が継続する場合には生活保護の受給資格は喪失します。ただし、おおむね6か月以内に再び保護を要する状態になることが予想される場合には、保護を要する状態になるまで生活保護の受給停止となります。(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)
なお、63条返還については、判例や裁決などの事例によるところが多いのでここでは割愛させていただきます。
相続放棄する場合の注意点
相続財産を受け取ると、生活保護受給資格が喪失してしまう場合、相続放棄を検討するかと思います。ただ、相続放棄にも種類があります。
相続放棄の申述(家庭裁判所にする手続き)
被相続人の住所地を管轄とする家庭裁判所において、相続放棄の申述をする方法があります。この手段をとった場合、相続人としての地位を喪失する身分行為をなるので、詐害行為取消の対象になりません。詐害行為取消の対象にならないということは、市役所側から相続放棄の行為を取り消すことができません。もし、生活保護の受給資格を喪失したくない場合、こちらの手続きを取ったほうが確実です。
裁判所への相続放棄はこちらから!(行政書士は裁判所への相続放棄申述サポートはできません)
遺産分割協議による相続放棄
少し難しくなりますが、相続人全員で話し合いをし、どの財産を、誰が相続するかを決めることを遺産分割協議といいます。その遺産分割で何も相続しない場合、共有持分を放棄・贈与した場合、形式的に相続放棄したと言えます。ただ、裁判所で行う相続放棄の申述と異なり、遺産分割協議で行う相続放棄は、詐害行為取消の対象となる可能性があります。これは、遺産分割協議は身分行為ではなく、財産行為であるとされているためです。
もっとも、判例では「詐害行為取消の対象となりうる」としたうえで、事実関係の下で取消が可能であることを示したにすぎず、すべての遺産分割協議が財産権になるとは言えません。実際に、判例(奈良地裁昭和27年11月8日、神戸地裁昭和53年2月10日)をみると、遺産分割が財産権を目的としない法律行為ではないとし、また、債務者の詐害性もしくは受益者の悪意を具体的に認定したうえで詐害行為取り消しを判断しています。
そのため、生活保護受給者や相続人が市役所を害する目的で、遺産分割協議等で、生活保護受給者の相続分を減らした場合には、詐害行為として、遺産分割協議が取消されてしまう恐れがあります。
相続分の放棄
相続放棄は要式行為である一方で、相続分の放棄は、要式行為ではない相続放棄と位置付けられており、事実上の相続放棄として活用されています。相続を知ってから3か月以上経過してしまった場合などに使われることが多いです。裁判所の申述をせずともでき、かつ、単独行為であるので、相続分の放棄をすることを相続人全員に通知すれば足ります。上記の「遺産分割協議のによる相続放棄」と同様な行為で評価されています。そのため、生活保護受給者の相続分を減らした場合には、詐害行為として、遺産分割協議が取消されてしまう恐れがあります。
相続分の放棄は、判例上、概ね認められていますが(※)、否定されている判決もあるので留意が必要です。
※「名古屋高決昭和43年1月30日家月20巻8号47項2033号213頁」、「大分家中津士支審昭和51年4月20日家月29巻1号83頁」、「東京地判平成24年11月9日平成24年11月9日平成24(ワ)4225号」
お気軽にお問い合わせください。080-8874-9690受付時間 9:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ