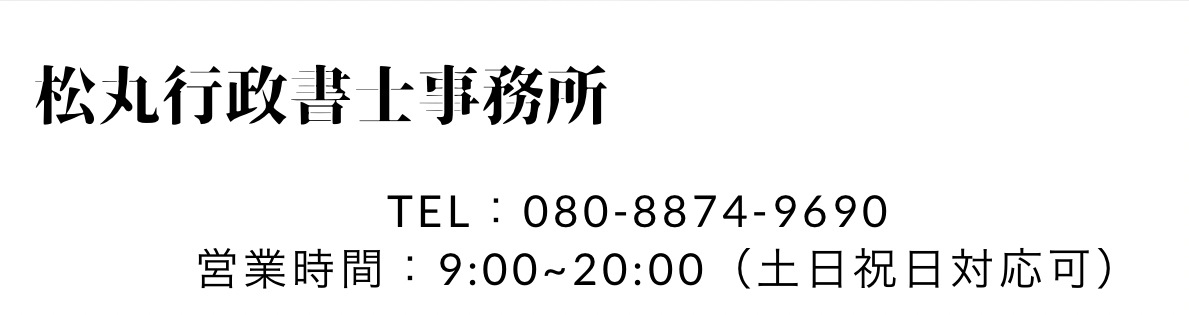葬儀費用と祭祀の主催者とは?相続トラブルを回避するために【国家資格者が解説】
相続の業務を行う際に、「葬儀費用ってどこまでを含むの?あと葬儀費用って相続財産から使えるよね?」とか「お墓の管理って誰がしていくの?」など聞かれることが多いです。
特に、葬儀費用については、話し合いの時間を取ることができず、遺産分割協議をしないまま、捻出し、相続財産の取り分をいざ決める際に、トラブルになることが多々あります。
今回は、葬儀費用の範囲や負担者やお墓の管理(祭祀の主催者)などを簡単に説明いたします。

葬儀費用の範囲とは
葬儀費用の範囲は、民法上では規定されていません。ただ、判例を中心にどこまでが葬儀費用になるか確認することはできます。
葬式費用の範囲は、死者をとむらうのに直接必要な儀式費用をいうものと解するのが相当であると判示されています。具体的には、棺柩その他葬具・葬式場設営・読経・火葬の費用(死亡届や火葬許可を含む)、墓地の代価、墓標の費用等を指しています。
もっとも、死者をとむらうのに直接な費用であっても、法要等の法事や石碑建立等の費用はこれに含まれないと解されるので、通夜と告別式の費用のうち寿司、料理、酒、ジュース、菓子等の各飲食、四九日法要、納骨代、葬儀後見舞客食費は、葬式費用には含まれないと考えられます。(昭和61年1月28日判決)
つまり、葬儀費用は、亡くなった方の弔いに直接的に関係があるものに限られます。
葬儀費用の負担者とは
では、葬儀費用の範囲は分かったとして、葬儀費用は誰が負担するものなのでしょうか。
端的にまとめると、葬儀費用は、原則、喪主が負担すべきものであるとされています。(東京地裁昭和61年1月28日判決)
喪主というのは、葬式を実施する者を指します。たぶん、皆様は、葬儀費用の負担は相続人もしくは被相続人の負担じゃないの?と疑問に思うことがあると思います。
これに関しては、判例上、「葬式は、必ずしも、相続人が実施するとは限らないし、他の者がその意思により、相続人を排除して行うこともある。また、相続人に葬式を実施する法的義務があるということもできない。したがって、葬式を行う者が常に相続人であるとして、他の者が相続人を排除して行った葬式についても、相続人であるという理由のみで、葬式費用は、当然に、相続人が負担すべきであると解することはできない。」と説明しています。確かに、葬式は、一般的に相続人である子が喪主となり、行うことが社会的に多いだけで、相続人が喪主になる法的義務はなく、また、身寄りのない人の場合は知人や公的機関が喪主になることもあります。
そして、喪主は、単に、遺族等の意向を受けて、喪主の席に座っただけの形式的なそれではなく、自己の責任と計算において、葬式を準備し、手配等して挙行した実質的な葬式主宰者を指すというのが自然であり、一般の社会観念にも合致するというべきであるとし、自己の意思に基づき、喪主の地位に就いたと解釈されます。
以上のことから、葬儀費用は、喪主が負担とされる理由になります。もっとも、死者が生前に自已の葬式に関する債務を負担していた等の場合であれば、相続財産から捻出することや、相続人でない者が葬儀費用を負担した場合において、相続人は、条理上、葬儀及び納骨などの諸費用のうち死者を弔うのに直接必要な儀式費用を相続分に応じて分担すべきであるとされた判例もあります。(津地裁平成14年7月26日判決)また、相続人間で相続財産を分配する際に、遺産分割協議書で、葬儀費用を相続財産から控除する協議を相続人全員で約束してもいいかと思います。なお、遺産分割協議書内で、葬儀費用を喪主を相続人とする場合は事前にご相談ください。相談はこちら!
祭祀承継人とは
あまり聞きなれない言葉かと思いますが、遺言書を作成するには基本的に記載されるものが祭祀承継人です。
祭祀承継人は、相続財産と別に、仏壇、位牌、家系図、お墓、遺骨(遺骨に関しては所有すること)を管理する者で、被相続人が指定する、または、家庭裁判所の指定で決まります。(慣習法という場合もありますが、裁判所は慣習法の存在を認めておりません)
裁判所が指定する場合、判例上、①被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって、被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち、または、②被相続人からみれば、同人が生存していたのであれば、おそらく指定したであろう者をその承継者とするとされています(東京高等裁判所平成18年4月19日決定)。なお、相続人が相続放棄したものでも、祭祀承継人になることは可能です。
祭祀承継人であっても、喪主になるべき法的美務は存在しません。そのため、祭祀承継人に指定されても、喪主になる必要はなく、葬儀を実施する義務も負いません。