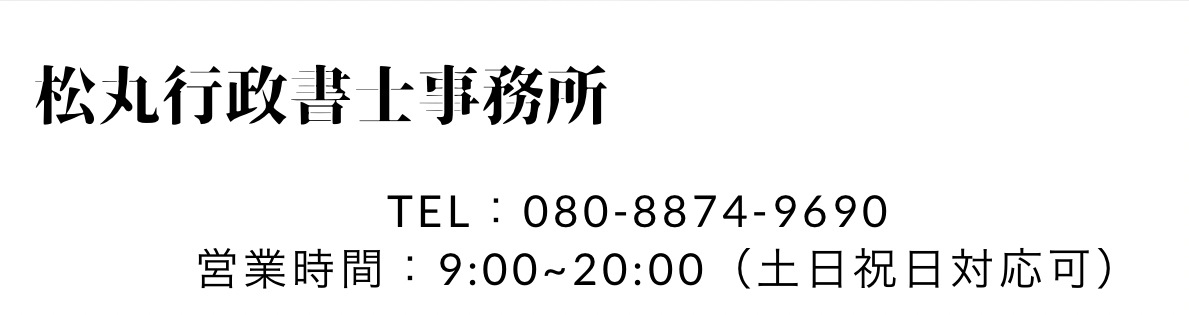遺言執行者の責任と賠償事例【遺言執行者がやるべきポイント】
遺言書を作成する際には、遺言執行者の選任と業務の範囲を記載することが多いです。当事務所でも、遺言書の依頼を受けた際には、90%以上で遺言執行者の説明をしております。
遺言執行者は相続発生時に、被相続人の代理人のような形で、不動産登記や預貯金の解約など様々な手続きができます。他方で、法律に規定された責任があります。この責任を果たしていない場合、相続人らに賠償責任を問われる可能性があります。
今回は、遺言執行者がどのようなケースの場合に、賠償責任を負う事があるのか説明していきます。

①受贈者の意思に反して、相続登記をした遺言執行者の責任
本事例は、被相続人であるAが、子であるBに、遺言書内で不動産を遺贈するとしていたにもかかわらず、Bがもう一人の相続人であるCとの関係性を考慮して、当該不動産を取得しない意思を表明していたにも関わらず、本遺言書の遺言執行者であるDが相続を原因とする所有権移転登記申請をした事例になります。
この事案に関しては、遺言執行者は大前提として、Bから委任を受けて、登記申請を行う必要があります。そのため、Dが登記申請する場合には、委任状を添付する必要があります(判例時報(2474号)を見る限りでは委任状の有無は分からなかったですが)。
遺言執行者は、遺言の内容を実現する責任がありますが、そもそも、遺言の放棄なども法令に準備されていたり、判例上、相続人全員(+遺言執行者)で遺産分割することで遺言書と異なる内容の協議をすることも可能なことを考えれば、あくまでも、受贈者の意思確認が必要であることは想像できるかと思います。
この事例の責任として、遺言執行者は、Bへの報酬支払ができない(拒否)結論になっています。
②遺言執行者の相続人に対する通知義務及び財産目録提示不履行
遺言執行者は、民法上で、相続人への財産目録の提示及び遺言執行の状況報告の義務があります。
本事例では、被相続人の法定相続人は、弟1と亡き弟2の代襲相続人である甥・姪の3人でした。被相続人は生前に遺言書を作成しており、遺言執行者に第三者を指定し、その者に遺贈する内容でした。遺言執行者らは、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合、相続人は遺留分侵害請求権を有しないことから、相続人になにも通知せず、遺言の執行をしておりました。そこで法定相続人らが、相続財産目録の交付、遺言執行者の就任通知・報告がなかったとして、遺言執行者らに対し、損害賠償を求める訴訟を提起した事案になります。
判例では、①遺留分を有しない相続人に対しても通知・説明・報告義務があること、②ただし、説明・報告義務について常にあるとはいえず、遺言執行の介入など妨害で執行を妨げること等総合的に勘案するとされています。(東京地方裁判所平成19年12月3日判決)
上記の判例では、慰謝料や調査費用・弁護士費用の支払いを遺言執行者に命じております。
遺言執行者と注意するポイント
まとめると、遺言執行者が注意すべきポイントは下記のようになります。
- 就任通知を遅滞なく相続人に通知する
- 遺言執行の説明や報告義務をする
- 遺言執行者として登記申請する場合、意思確認を必ず行う
なお、遺言執行者は弁護士や行政書士などの専門家に委任することも可能です。
また、遺言書に遺言執行者の選任がない場合、被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に申立することで、遺言執行者を選任する審判を受けることも可能です。詳細はこちらから。