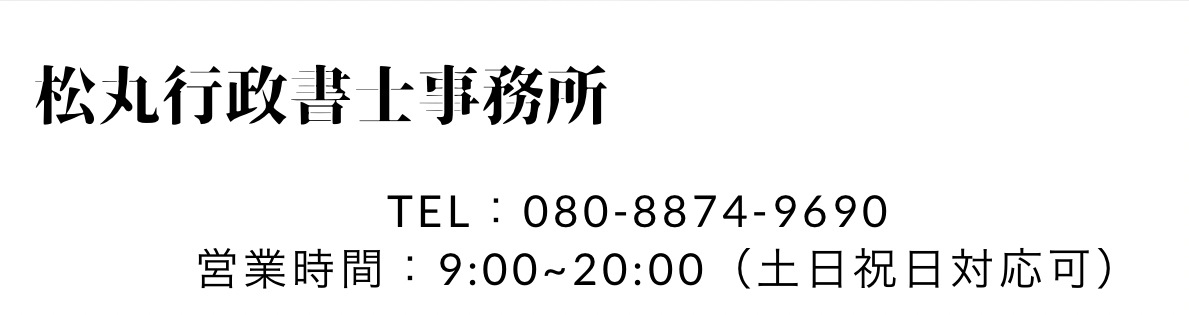扶養できる者がいても生活保護申請できる?扶養照会を断る理由【専門家の行政書士が説明】
生活保護申請を行うと、原則、親族の住んでいる場所に扶養ができるか否かを確認するために扶養照会が実施されます。
そのため、生活保護の利用を検討する際、多くの申請予定者が親族との関係、特に民法上の「扶養義務(ふようぎむ)」について不安になる人が少なくありません。当事務所でも、ご相談時に扶養義務の照会がされるかどうか多くの人に聞かれます。「親族に迷惑をかけたくない」「親族が経済的に支援できる状況にない」「関係が悪化しており頼れない、あるいは親族側が扶養したくないと考えている」といった状況だと、不安はさらに多くなります。
しかしながら、法制度と実務運用を正確に理解すれば、親族に扶養義務が存在すること自体が、生活保護の利用を妨げるものではありません。生活保護制度は、扶養義務者からの実際の援助が得られない場合にも、必要な支援を提供するための仕組みを備えており、現に多くの市町村がこのような運用を行っております。
今回は、行政書士の専門的観点から、日本の民法における扶養義務の法的根拠と範囲、生活保護法におけるその位置づけ、福祉事務所が行う「扶養照会(ふようしょうかい)」の実態、そして扶養が期待できない場合の具体的な取り扱いについて解説します。

扶養義務の根拠
日本の民法は、一定範囲の親族間(直系血族)に扶養義務があることを民法第877条で定めています。ここでいう「直系血族」とは、父母、子、祖父母、孫など、本人から見て縦の血縁関係にある者を指します。もちろん養親子関係も、そして、「兄弟姉妹」には、両親を同じくする場合だけでなく、片親のみを同じくする場合も含まれます。
また、夫婦においては、民法第752条で「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めており、夫婦間においてはより扶養義務が 求められています。
特別の事情があるときには、家庭裁判所の審判によって、「三親等内の親族」(例:おじ、おば、甥、姪など)にも扶養義務を負わせることができると定めています。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
生活保護制度と親族扶養の関係性
補足性の原則:「扶養」の優先順位
生活保護法第4条第1項では、保護は「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件としてます。そして同条第2項で、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定されており 、これは「保護の補足性の原則」と呼ばれ、公的な扶助よりも私的な扶養(親族からの援助など)や他の社会保障制度が優先されることを意味します。
「優先」の意味:扶養は保護の「要件」ではない
「扶養が保護に優先する」という規定の具体的な意味ですが、これは、扶養義務のある親族が存在するという事実だけで生活保護が受けられないという意味ではありません。
この規定が意味するのは、もし扶養義務者から実際に金銭的な援助(仕送りなど)が行われた場合に、その受け取った金額を収入として認定し、生活保護費から差し引くということであり、扶養義務者が存在する、あるいは扶養能力があるかもしれないという可能性だけでは、保護の要否判断(つまり、保護を受けられるかどうかの決定)に影響しません。
これは、1950年(改正前の旧)生活保護法には、扶養義務者が扶養可能である場合には保護を受けられないという欠格条項が存在したが、現行法では撤廃されている ことからも言えます。
制度設計の意図:申請者の権利保護
生活保護法の構造は、まず困窮している申請者本人への支援提供を第一優先にしています。憲法第25条の生存権保障に基づき、国は最低限度の生活を保障する義務を負うため、扶養義務者からの扶養が実際に行われない場合、福祉事務所はまず保護を開始・実施し、その上で、扶養義務を果たさない義務者に対しては、別途、生活保護法第77条に基づく費用徴収という手続き(後述)が行われます。つまり、申請者の保護を受ける権利の実現が、扶養義務の履行問題よりも優先される仕組みとなっています。
「扶養照会」とは何か?
生活保護の申請を行うと、市町村は申請者の親族に対して「扶養照会(ふようしょうかい)」と呼ばれる連絡を行うことがあります。
目的と定義
扶養照会とは、福祉事務所が生活保護を申請した人の親族に対し、申請者に対して経済的または精神的な援助を行うことが可能かどうかを問い合わせる手続きです 。その目的は、生活保護法第4条第2項の補足性の原則に基づき、利用可能な私的扶養(親族からの援助)がないかを確認すること、および、親族からの援助があるにも関わらず生活保護費を受け取るような不適切な受給を防ぐところにあります。
法的根拠と実施基準
扶養照会の実施は、生活保護法に直接的に全てのケースで義務付けられているわけではなく、主に厚生労働省の通知や実施要領といった行政内部のルールに基づいて行われています 。近年、この運用は見直され、照会は「扶養義務の履行が期待できる者」に対して行うものとされている 。 もっとも、全ての市町村がこのような通知や要領を守っているわけではありません。これは、このような通知や要領には法的拘束力がないためです。
照会対象者の範囲や内容
原則として、照会は申請者の三親等内の親族(例:父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、おじ・おば、甥・姪など)に対して行われる可能性があります 。ただし、実務上は、より近しい関係にある親族(配偶者、親子、兄弟姉妹など)が主な対象となることが多いです。
扶養照会の書面では、通常、申請者への経済的な援助(仕送りなど)や精神的な支援(相談に乗るなど)が可能かどうか、また、回答する親族自身の収入や生活状況などについて確認されます。
扶養照会は回避できるか?照会が行われないケース
扶養照会は、全ての親族に対して一律に行われるものではありません。
近年、申請者本人の意向が重要視されており、申請者が特定の親族への連絡を望まない場合、その理由を丁寧に聞き取り、その理由が「扶養義務履行が期待できない」状況に該当すると判断されれば、照会を行わないことが多くなっています。厚生労働大臣も国会答弁で扶養照会は義務ではないと明言している 。 もっとも、上記のようなケースに該当しても、扶養照会を行う市町村はあります。
法的にも、扶養義務は本人の意向がなければ、求めることは難しいと言えます。理由としては、申請者である要扶養者が持つ扶養請求権は、処分や譲渡ができない一身専属権であるためです。この権利は、扶養請求をした際に生ずるものである(判例など)ことから、扶養を求めるかどうかは本来的に扶養義務者の自由であり、扶養義務者に扶養するか否かは、扶養権利者である保護申請者の意思に任せる問題であること、また、扶養請求権は一身専属権の性質を有することから代位することができないことから、照会を行わないことが多くなっているのではないかと思います。
もっとも、生活保護受給者が相続人となる相続が発生した場合、家庭裁判所に申述をする相続放棄をした場合でなく、遺産分割における相続放棄をした場合には、生活保護費の返還請求の対象になる可能性が高いので、注意したほうがいいでしょう。
ためらわずに相談を:千葉県での支援
これまでの解説で明らかなように、親族に扶養義務があることや、扶養照会という手続きが存在すること自体を理由に、生活保護の利用を諦める必要はありません。
生活保護の受給資格は、あくまで申請者世帯の収入や資産が国が定める最低生活基準に満たないか、稼働能力を活用してもなお生活困窮状態にあるか、といった客観的な状況に基づいて判断されますし、 扶養義務者からの援助は、実際に提供された場合に収入として考慮されるに過ぎません。
「扶養したくない」「頼りたくない」といった感情や、複雑な家族関係も、現実の問題として存在し、現在の生活保護制度の運用、特に扶養照会に関する近年の改善は、こうした個別の事情に配慮し、申請者の意向を尊重する方向で進んでいます。概ねですが、、、
千葉県内にお住まいで、生活上の困難に直面し、生活保護の利用を考えている方は、どうか誤った情報や先入観にとらわれず、お住まいの自治体の福祉事務所や、法律・制度の専門家である行政書士に相談することを推奨します。
まとめ:行政書士による千葉県での生活保護申請サポート
行政書士は、生活保護制度に関する専門知識に基づき、申請手続きを円滑に進めるための支援を行うことができるます。
また、当社は特定行政書士という「行政書士の中でも10%しか有していない」認定を受けた行政書士になりますので、審査請求も可能です。
具体的には、以下のようなサポートが可能です!
- 生活保護制度の内容、受給要件、申請手続きについて、個別の状況に合わせて分かりやすく説明する。
- 申請に必要な書類の収集・作成を支援し、不備なく正確な申請を行えるよう助言する。
- 福祉事務所への相談や申請に同行し、申請者の状況や意向を的確に伝える手伝いをする 。
- 扶養照会に関して、申請者の意向を踏まえ、照会を回避すべき理由(音信不通、関係性の悪化、DV等)を整理し、厚生労働省の通知等に基づき福祉事務所に適切に説明するための助言を行う。
- 申請プロセス全体を通じて、申請者の権利が守られるようサポートする。
生活保護は、生活に困窮する国民が利用できる、憲法に基づく権利です。扶養義務や親族関係に関する悩みがあっても、一人で抱え込まず、まずは専門家への相談を検討してください。お問い合わせはこちら!
お気軽にお問い合わせください。080-8874-9690受付時間 9:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]
お問い合わせ