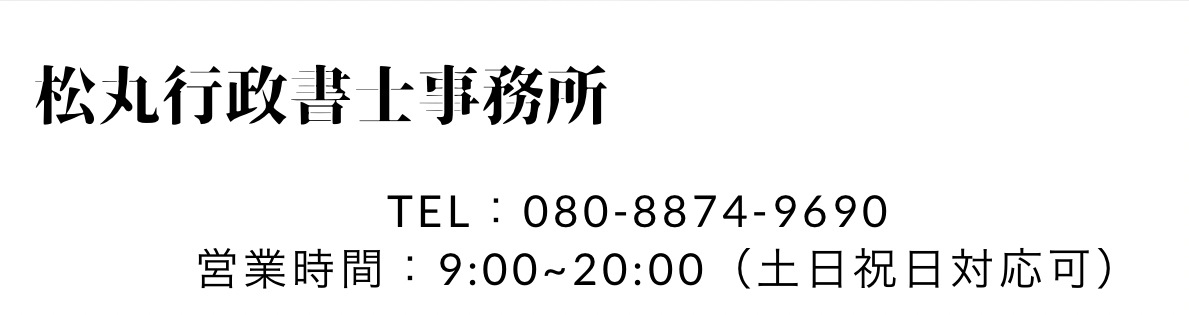生活保護費を返還(63条)しなければならないケース【行政書士が解説】
生活保護の受給者は、預貯金など財産が一定以上あるにも関わらず、生活保護費を受給したときは、返還しなければならないとされています。
もっとも、あくまで、受給者側に返還義務があるのみで、市町村は、返還義務を必ず請求するわけではないです。(請求するのに行政の裁量が認めれている)
では、どのようなケースの場合には、63条返還請求がされて、その請求が認められるのでしょうか。今回は、判例や裁決を使って説明させていただきます。
生活保護法(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
※相続をした際に、63条返還請求をされないか否かはこちらをどうぞ!

事例①(東京地裁平成29年2月1日)
本件は、生活保護を受けている原告が、福祉事務所の職員の過誤により、原告が収入として申告していた原告の長女に係る児童扶養手当について収入認定がされていなかったこと及び原告について冬季加算の削除の処理がされていなかったことによる生活保護費の過支給が生じていたことにつき、福祉事務所長から,生活保護法(以下「法」という。)63条に基づき、過支給に係る生活保護費の全額を返還すべき額とする旨の決定を受けたことから、①現に資力のない被保護者に対する返還決定は同条に違反して違法であり、②仮にそうでないとしても,本件処分には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、③さらに手続上の瑕疵として聴取・調査義務違反があるから、本件処分は違法である旨主張して、その取消しを求める事案である。
つまり、本件の主張は、①63条返還違反、②裁量権の逸脱・濫用、③手続ミス(63条は行政手続法上の不利益処分なので聴聞等が必要であった)になります。
法令上から導き出るもの・あてはめ
法63条は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた被保護者に対し、その受けた保護金品に相当する金額の全額の返還を一律に義務付けるのではなく、その金額の範囲内において保護の実施機関の定める額の返還を義務付けるにとどまる。これは、法が、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としていること(1条)に鑑み、現に保護を受けている被保護者や要保護状態を脱して間もないかつての被保護者に対して、現に返還に耐え得る資力を有するか否か等にかかわらず、その受けた保護金品に相当する金額の全額を一律に返還させたのでは、最低限度の生活の保障の趣旨に実質的に反するおそれや、その自立を阻害することとなるおそれがあることから、個々の場合に被保護者に返還を求める金額の決定を、当該被保護者の状況をよく知り得る立場にある保護の実施機関の合理的な裁量に委ねたものと解される。
したがって、法63条に該当する被保護者について、その資産や収入の状況、その受けた保護金品の使用の状況、その生活実態、当該地域の実情等の諸事情に照らし、返還金の返還をさせないことが相当であると保護の実施機関が判断する場合には、当該被保護者に返還金の返還をさせないことができるものと解される反面、保護の実施機関による返還金額の決定が、上記の諸事情に関し、判断の基礎とされた事実に誤認があること等により事実の基礎を欠くこととなる場合、又は、事実に対する評価が合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が法の目的や社会通念に照らして著しく妥当性を欠くと認められる場合には、保護の実施機関に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となると解するのが相当である。
※63条は、過支給を事後的に調整することもでき(事例研究行政法391頁)、行政庁の判断ミスにより過支給がなされた場合にも適用できる。
※厚生省の通達(平成24年7月23日付社援保発0723第1号)によると、63条の返還は、原則、全額を返還対象とし、全額返還により保護世帯の自立が著しく阻害されると認められる場合は、①盗難等の不可抗力により消失した額、②家屋補修の一時的な経費で保護変更申請をしていれば支給が認められていた額、③世帯の自立更生のためにやむを得ない用途にあてられたもので、地域住民と比べ、社会通念上容認されうる程度のものは、控除しても差し支えないとされている。本件においては、③に該当するか否かが問われる。
※あてはめについては、こちらの7頁よりご参照ください。
結論
本件処分は、①被保護者の資産や収入の状況等検討すべき諸事情についての具体的な事実の基礎を欠き(事実誤認)、また、②判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないことによりその内容が法の目的や社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものと認められる(考慮不尽)から、福祉事務所長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして、違法というべきである。
事例②(東京高判令和2年6月8日)
認知症により意思能力を欠いている者に対し、市町村長による職権で生活保護の開始を決定し、保護費約600万円(うち医療扶助費500万円)を支給しました。その後、当該市町村の福祉事務所長は、生活保護受給者が資力を有するものであったとして、給付した保護費全額の返還を求める決定をしました。
その後、生活保護受給者は死亡し、その者の相続人は、被相続人が後期高齢者医療の被保険者として医療を受けた場合の自己負担分の出費しか免れていないことから、保護費全額の返還を求める決定には裁量権の範囲を逸脱した違法があると主張し、その取り消しを求めて訴えを提起しました。
つまり、後期高齢者の医療費1割なので、本来の負担額は約50万円でよかったところ、生活保護を開始したことで、本来負担しなくてもよかった額(450万円)の請求を市町村長からされたことが、裁量権の逸脱と主張したということです。
法令・あてはめ
裁判所は、保護費の返還額の減額ができるのは、平成24年通知の定める場合に限られないものの、実質的に不利益を課す処分となりうる保護を行う場合には、保護を受ける相手方に、保護を受けた場合の不利益の内容を説明して十分な理解が得られることが不可欠の前提があります。
本件では、生活保護決定に際して、給付される医療扶助について将来その全額の返還を求められ、著しい経済的不利益を被ることになるのに、少なくとも相続人の理解を得ないままに職権で保護の決定が行われた結果、相続人の意思とは関係なく、何らの予告もなく著しい不利益を課されることになった(手続き上の瑕疵?)。また、生活保護法の運用にあたっても、社会保障制度全体の中でその運用を考えるべきであり、返還決定が後期高齢者医療の被保険者であれば負担を要しなかった範囲の保護費の返還を求めている部分については裁量権の範囲を逸脱した違法がある。
なお、東京都が裁決した事案(63条返還に対する審査請求。令和3年6月17日付の63条返還に対する審査請求。総法不服第120号)では、上記事案と同様のケースであったが、63条返還の処分が、被相続人の死亡後に行ったと事案と、また、厚生省の63条返還の取り扱いが変わっていないとし、棄却している(=本来不要の範囲であった医療費を含めて返還しろというもの)
もっとも、この裁決については、疑義があると考えております。被相続人の債務は、相続により遺産分割することなく、相続人に承継されます。そう考えると、被相続人の死亡の前後で返還請求の判断が変わるのは不当であると言わざるを得ません。