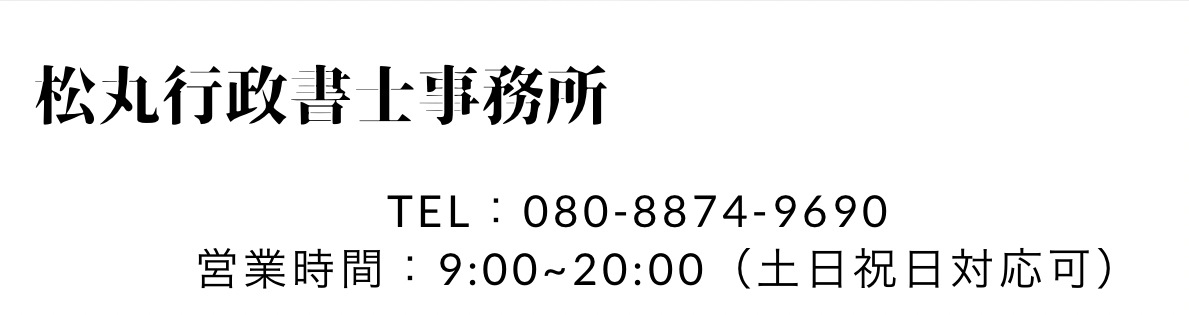何が相続財産になる?遺産分割が必要な財産も紹介【国家資格者が解説】
相続や遺産分割協議書の作成相談を受けた際に、「何が相続財産になりますか?」「遺産分割はなにをすればいいですか」と相談されます。
金銭や不動産であれば、身近な財産なので、理解しやすいですが、あまり馴染みのない財産、たとえば、株・証券や保険などは、遺産に含まれるか悩むところだと思います。
今回は、どのような財産が相続財産になり、その相続財産は遺産分割する必要があるのか説明させていただきます。
なお、税務上、相続財産に該当するかは、別途税理士等に相談ください。

相続財産になるもの
相続が発生(亡くなった)すると、相続開始時点で、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産(債権・債務を含め)は、原則としてすべて相続の対象となり、相続人に承継されます。なお、相続人が複数いる場合には、共有となります。ただ、これだと財産として扱いにくいケースがあるので、遺言書などがある場合を除き、遺産分割することがほとんどかと思います。
しかし、すべての財産が相続財産になるわけではありません。そして、相続財産に該当しても、遺産分割が必要でない財産もあります。具体的には下記のように分けることができます。
| 相続財産になる | 相続財産にならない | |
| 遺産分割の対象 | 不動産、預貯金、株式 遺産分割後の家賃債権 | なし |
| 遺産分割の対象外 | 可分債権 死亡退職金 分割前の受取家賃債権 | 生命保険 遺族年金・企業年金 祭祀財産、葬儀費用、香典 |
では、各財産は、どのような理由で分けれているのでしょうか。上記の財産をすべて紹介するのは難しいですか、一部のみ説明させていただきます。
※葬儀や祭祀については、こちらの記事を参照ください。
預貯金
預貯金とは、ゆうちょや各種金融機関に有してる口座にある金銭のことです。難しいですが、私たちが銀行にお金預けている行為は、銀行にお金を貸している行為で言えるので、銀行に対して債権を有していると言えます。
このような債権は、相続財産に該当するのは理解しやすいかと思いますが、債権(可分債権)は、各相続人が相続発生から独立して行使できるとされています(民法427条)。預貯金は、可分債権のため、相続の発生に法律上当然に分割され、各相続人が各相続に応じて当然に分割取得すると解されており(最判昭和29年4月8日)、遺産分割の対象外になっていました。
しかし、預貯金は、他の可分債権と異なり、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権その他の預金債権は、その性質が現金と大きく異ならず、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である(最大決平成28年12月19日)と判示されたことから、遺産分割の対象となりました。
そのため、遺産分割がされない状況で、法的に預貯金を引き落とすことは原則できません。なお、一定の範囲内に限り、引き落とすこともできます。
株式
株式も相続財産に含まれます。ただ、株式は、他の財産とは性質が異なっており、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはありません(平成26年2月25日)。この理由は、株式とは、株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し、 この地位に基づき、 剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利などのいわゆる自益権と、 株主総会における議決権などのいわゆる共益権とを有することから、このような権利の内容及び性質に照らせば、 当然に分割されないとされています。そのことから、株式を単独で相続、または、換価して金銭で分割する場合、遺産分割を行う必要があると言えます。なお、株式は、準共有(民法246条)として処理されると解されております。
生命保険
生命保険は、結論からいうと、相続財産に該当しません。この理由は、 生命保険は、保険契約に基づき、被保険者の死亡により保険金受取人に指定された者の固有の権利として発生するため、遺産分割相続開始時に被相続人に帰属していた財産とはいえないからです。なお、受取人の指定がなく、約款に「相続人に支払う」との規定があっても、生命保険金は相続人固有の権利となるため、相続財産にはあたらず、遺産分割の対象にはならない(最判昭和48年6月29日)とされています。(最高裁判所平成16年10月29日決定)。
また、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には、相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれているものと解するのが相当であるので、相続分の割合により保険金を取得することが可能です(最高裁判所平成6年7月18日判決)。
なお、留意していただきたいのは、保険受取は、原則として特別受益(相続財産計算時に含まれない)には当たりません。とはいえ、保険金の金額により、保険金受取人として指定された相続人と他の相続人との間に「民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい不公平」が発生した場合、そのような著しい不公平が発生するときは民法903条を類推適用して特別受益になります。