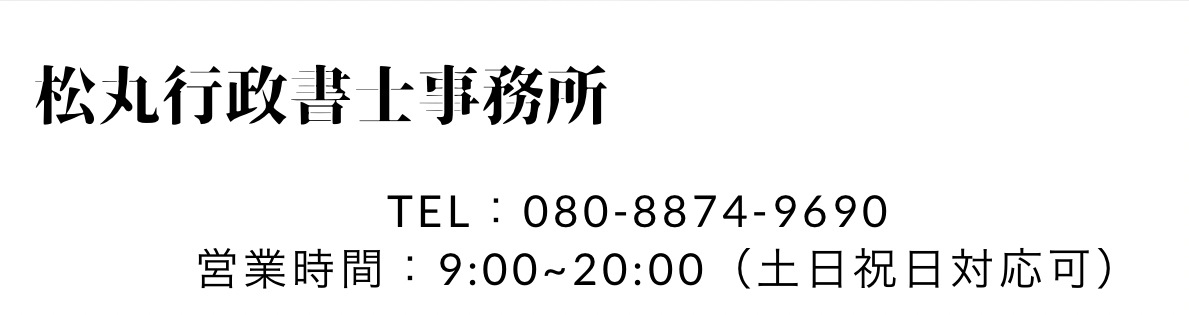審査請求等にも使える三段論法とは【行政法を事例に解説】
法律問題の解決には、三段論法と言われるものが使われます。聞こえの良い方法ですが、最初は理解しづらく、慣れるまで苦労します。ただ、判例や裁決(地方自治体が行う審査請求に対する判決みたいなもの)は、ほぼ全てで三段論法が使用されています。
行政書士の中でも研修を受けた10%の特定行政書士は、自分の取り扱った業務(来年よりもは自分の取り扱った業務以外でも)に関して、行政庁に審査請求をすることができます。そのため、裁判などの紛争業務をしない行政書士であっても、特定行政書士を有している以上は、三段論法を学ぶ必要があると思います。
今回は、どのように三段論法を使えばいいのか、実際の事案をもとにして、解説します。

三段論法の基本
三段論法は、①条文文言の確認、②文言を法令解釈、③あてはめのステップで進んでいきます。
例えば、刑法第130条をで確認してみましょう。刑法第130条(住居侵入等)は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する」とされています。①条文の確認は、ここで問題になりそうな部分につき、行っていきます。
事例として、金銭を盗むことを目的に、近隣の自宅の堀によじ登った行為で考えてみましょう。この場合、堀をよじのぼった行為が侵入にあたるかどうか検討しなければなりません(正当な理由がないというのは、金銭を盗む目的で記載されている以上、ここでは議論の余地がないです)。
条文の確認をした後は、その文言を法令解釈していく必要があります。解釈にはいろんな方法がありますが、基本的には最高裁判例や学説から引用するのが一般的ですが、上記で議論されていない場合は、法の目的や趣旨から解釈していくことになります。なお、「侵入」とは、「住居権者の意思に反する立ち入りをいう」と法解釈されることが一般的です。
法解釈をした後は、あてはめに入ります。あてはめは、法令解釈により示された内容が事例にも該当するか確認する作業になります。本事例でいえば、自宅の堀によじ登る行為は、よじ登っている最中であれば、立ち入りに該当しないかもしれませんが、よじ登る行為そのものが、立ち入りに向かっている行為といえ、かつ、よじ登る行為を住居権者が見た場合には、住居権者がその行為に反対すること極めて高いと言えます。よって、自宅の堀によじ登る行為は、侵入しているといえます。
ここまでが三段論法の流れになります。文言の解釈は暗記することが多い分野になりますが、あてはめに関しては、事例をいかに細分化し、解釈に該当するか説得する段階になります。
事例で解説【行政法分野で】
では、実際にどのような使われるのかもう少し、複雑な事例で確認してみましょう。
事例としては、児童が親に虐待されたと評価され、児童相談所が当該児童を一時保護した事案です。一時保護は必要がない違法な処分だとし、児童の親が審査請求した事案になります。
※なお、本件は架空の事例になります。
①文言確認
まず、児童福祉法第33条第1項において、「児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第六条の六第一項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。」とし、児童相談所長は、必要があると認めるときは児童の一時保護を行うことができると規定されています。
今回、児童の両親は、必要のない処分だとして、一時保護の違法性に基づき、一時保護の取消裁決を求めています。そのため、「必要があると認めるとき~(略)~できる」が問題になります。
②法令解釈
では、第33条の「必要があると認めるとき」の法令解釈をしていくんですが、ここでは、判決(平成27年3月11日東京地方裁判所判決)から検討していきましょう。
上記の判決では、「法第33条第1項において一時保護の要件が「必要があると認めるとき」との文言により規定されること及び児童の福祉に関する判断には児童心理学等の専門的な知見が必要とされることからすれば、児童に一時保護を行うか否かの判断やどのような期間一時保護を継続するかの判断は、いずれも処分庁の合理的な裁量に委ねられていると解するのが相当である」とされています。つまり、一時保護には、児童に関する専門知識が必要とされていることから、行政庁の裁量にゆだねましょう、ただ、裁量の範囲を逸脱したり、濫用した場合には、合理的とはいえないので、違法な処分になります。
なお、もう少し踏み込んで説明すると、本条文は、条文の文言が抽象的なので、要件裁量があると判断でき、条文の文言の語尾が「~できる」となっていることから効果裁量があると言えます。
③あてはめ
最後に、法令解釈した文言に、あてはめをしていくのですが、今回は裁量に関する事例なので、事案を通してみて、裁量の逸脱・濫用の有無を検討します。具体的には、専門技術的裁量、事実誤認、目的や動機違反、信義則違反、比較原則違反、他事考慮及び考慮不尽などを見ていきます。あてはめは大変なので、一部裁決を参照しております。
①処分庁は、本児らに対し、自宅ではない別のところに泊まるか、審査請求人の自宅に帰るか選択肢を提示し、別のところに泊まる場合には、しばらく学校に通うことが難しくなるものの、児童の身体かつ精神的な安全を確保できること、児童の両親とは処分庁内で、定期的に面談でき、完全に繋がりが途切れるわけではないと伝えており、現状、児童の利益に適うものであることを説明したところ、自宅ではない別のところに泊まる意向を確認した。そのため、別法第33条の3の3の規定(意見聴取等措置)に基づき、児童の最善の利益を考慮し児童の意見又は意向を勘案したものと認められる。
②審査請求人は、本件処分があった日にごみ箱を蹴ったことは、長女を起こすためにしたことであると主張しているが、同日に本児らが自宅に帰ることに不安を感じていると述べていたことや、処分庁が心理検査を実施したところ、急激なストレスによる解離症状がみられている。よって、推察理由の如何にかかわらず、本児らに著しい心理的外傷を与える行為であり、児童虐待防止法第2条第1項に規定する「児童虐待」に該当するものと解される。
③処分庁は、児童から、「親がよく私たちの前で喧嘩をしている」ことや、「審査請求人の機嫌を損ねると、ドアや壁を叩き、破壊している」ことをヒアリングしている。これらの行為は、児童の精神を害する行為と言え、心理的虐待と評価せざるを得ない。また、児童の通っている小学校の担任教諭から、放課後に残っている学習をしている日が多く、生徒に事情を聴いたところ、「今日はお父さんが早く帰ってくるから学校で宿題をしてから帰る」や「早く帰ってくると宿題が進まない」と聞いており、現在の家庭状況に何かしら問題があることが考えられる。これにより、児童の安全確保と家庭状況の調査が必要と判断したため、本件処分を行っており、これはガイドラインに規定されている虐待等の理由によりそのこどもを家庭から一時引き離す必要がある場合に該当するものと認められる。
以上を総合的に判断すれば、処分庁が、本児らが自宅に帰ることに不安を感じ、帰宅拒否の意向を示していることを踏まえ、児童相談所における援助方針会議により、審査請求人からの心理的虐待の疑いがあり、児童の安全確保と家庭状況の調査のため一時保護が必要であると判断したことについては、処分庁の合理的な裁量の範囲内にあるものと認められる。