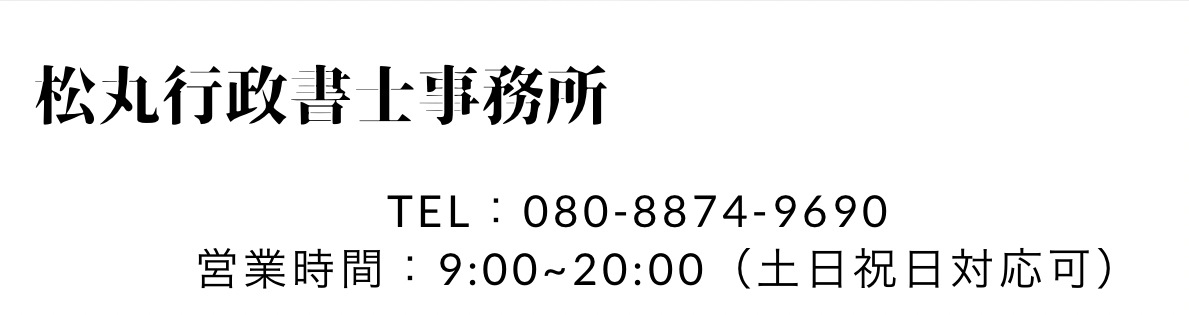戸籍から除籍されたけど亡くなっていない!?【高齢者削除について】
あまり多くはありませんが、業務中に戸籍を扱っていると、「高齢者につき死亡と認定」の旨とその許可年月日が記載されていることがあります。
これは「高齢者職権消除」といいます。もっとも、「死亡」という記載があったとしても、この記載をもって各種相続手続かどうかはまた別の話になります。
今回は、高齢者職権消除とはどのような制度なのか解説していきます。

高齢職権削除されるケース
私が見てきていたケースの中で、高齢職権削除されていた事例(片手で数えられるケース)ですが、①住所が職権削除されている高齢者(不在者であること)、②災害や戦争などあった場合(千代田区とか台東区とか多い)のパターンがありました。
ただ、具体的にどのような要件で職権削除がされるかは不明です。行政としても、要件が定まっていると、柔軟に対応することができないので、現状のような行政側の判断で削除できるほうが使い勝手がよさそうです。
高齢職権削除が行われると、戸籍上(厳密にいうと身分事項)に「高齢者につき死亡と認定令和〇年〇月〇日付許可同月同日除籍」または「年月日及び場所不詳死亡令和〇年〇月〇日付許可を得て同月同日除籍」に記載されます。どちらの文言でも効力は同じです。
高齢職権削除されていたら
高齢職権削除は、その人が死亡したような書きぶりですが、なんとも、この記載だけでは、当人が死亡したとみなしてくれません(昭和32年12月27日民事三
発1384号)。そのため、法定相続情報・遺産分割のが作成できず、相続登記・放棄、銀行口座の解約等もできません。(そもそも財産があるかどうかわからないですが)
対応方法
高齢職権削除された場合、どのような手続きを踏まばいいのでしょうか。だいたいは次のケースに分かれると思います。
・失踪宣告の申立
・認定死亡
・不在者財産管理人(所有者不明)の選任申立&供託
まず、職権削除された日から7年を経過している場合には、裁判所で失踪宣告の申立を行いましょう。失踪宣告が認められれば、法律上でその者が死亡したと推定されます。また、認定死亡の制度は、災害などで死亡した人がいる場合に使われる制度です。基本亭には、行政側が行うものですが、実務上、利害関係人も利用できるような制度のになっています。
他方で、職権削除された日から7年を経過していない場合や明確な死亡が確認できない場合には、不在者財産管理人の選任申立を考える必要があります。もっとも、こちらは不在財産管理人を就任させることになるので、100万円ほど費用がかかってきますし、そもそも高齢者職権削除ではあまり使われない制度(実務上は相続人の所在が不明の時に使います)なので、失踪宣告ができるまでは対応せずでもいいかもしれません。